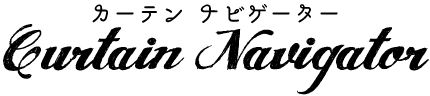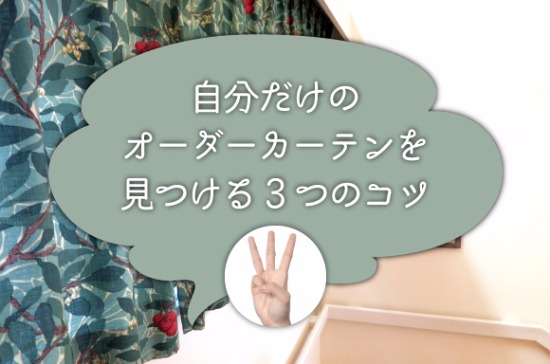カーテンは外からの視線を遮るためだけでなく、窓を装飾する意味でもインテリアに欠かせないアイテムです。
家の窓はいくつもありますが、それぞれのカーテンを選ぶときはどういう基準で選びますか?
カーテン生地にはさまざまな種類があり、価格もまちまちです。デザインも豊富にあるので、なにを選んでいいのか迷ってしまいますね。
デザイン重視、機能重視、価格重視など選ぶ人それぞれでしょう。
ここではいろいろな観点から窓に適したカーテン生地の選び方をご紹介します。
カーテンの選び方の基本。ドレープカーテン・シアーカーテンの役割とは
カーテンは、厚手のドレープカーテンと薄手のシアーカーテンをセットにすることが一般的です。それぞれどのような役割があるでしょうか。
ドレープカーテンの役割

装飾性
多彩なデザインやカラーバリエーションで窓空間を装飾します。
遮蔽効果
外からの視線を遮りプライバシーを守ります。
遮光効果
昼間は太陽光を、夜は室内光を遮ります。
断熱効果と遮熱効果
外気の温度は、約7割が開口部である窓から室内に伝わります。カーテンをかけることで、夏は外の熱気を遮断し、冬は室内の暖気を外へ逃すことを防ぎます。
遮音効果
室内の音がカーテンをすることで吸収され、外に漏れることを防ぎます。また、外からの騒音も小さくする効果があります。
シアーカーテンの役割

装飾性
繊細な生地で、昼間の窓空間を装飾します。
遮蔽効果
昼間ドレープカーテンを開けている時に、太陽光を取り入れつつ外からの視線を遮ります。
適度な採光性
直射日光を和らげ、部屋に適度な太陽光を取り入れます。
UVカット効果
有害な紫外線をカットする効果があります。
生地から選ぶカーテン

厚手の生地のドレープカーテンには、織物やプリント生地があります。織物生地は繊細で複雑な柄を織ることも可能ですが、高価であるとも言えます。織物生地に比べて、プリント生地はよりリーズナブルなものも多くあります。
織物生地、織り方で変わる特徴や魅力
織物には何通りもの織り方がありますが、代表的な織り方には三原織組織と呼ばれる平織、綾織、朱子織があります。
ジャガード織物
ジャガード織物はジャガード機を用いて、三原織組織を複雑に組み合わせ、模様をつくる織物で、繊細で大きな模様をつくり出せる特長があります。

1800年頃にフランスの発明家によって発明されたジャガード機は、紋紙と呼ばれるパンチカードに穴を開け、その穴の位置でタテ糸の操作を操り模様を織り上げる自動織り機です。穴の空いているところでタテ糸が上下し、穴のないところで動きが止まります。当時の織物は各糸を大人数で分担しながらの作業でしたが、ジャガード機はパンチカードにタテ糸の動きをプログラミングして織る画期的な発明でした。明治時代に初めて日本に伝わり、現在ではコンピュータ制御され、より繊細で大きな模様が織れるように進化しています。
複雑な模様ならプリントでも良いと考えるかもしれませんが、織物の魅力は凹凸がある立体的な質感にあります。カーテンもジャガード織りの生地は、立体的に浮き上がった模様がラグジュアリーなファブリックとして長年愛され続けています。
ドビー織物
ジャガード機の後に登場したのが、ドビー機です。ドビー機はタテ糸とヨコ糸を交互に織ることで、規則正しい単純な模様を作り出すことができます。大きな模様はジャガード織りほど表現できませんが、縦糸のパターンを変えることで、小さな幾何学模様やストライプ柄、チェック柄など、さまざまな連続模様を織り出すことができます。
ドビー機は、カーテン生地にも多く使用され、ジャガード織りほど高価ではなく、カジュアルなファブリックとして人気があります。
プリント生地

プリント生地は、織り上がった状態の「生機(きばた)」と呼ばれるベースになる布を、晒したり漂白するなどの処理を施したあと、絵柄をプリントします。多彩な柄やデザインが可能なプリント生地には、フラワー柄やリーフ柄から、子ども向けの動物や車の絵の生地もあります。
生地へのプリントには、アナログプリントとデジタルプリントの2種類があります。
アナログプリントは、昔ながらの方法で大きなスクリーンやロールを使用し、絵柄に使う色の数だけ版を作り、1色ずつスクリーンやロールで絵柄をプリントしていきます。言わば版画のような仕組みです。
アナログからデジタルの時代になり、デザインの幅が広がりました。デジタルプリントはインクジェットプリントとも言い、プリンターで色を吹き付けながらプリントします。パソコンで使用するインクジェットプリンターと同じです。複数の色でも一気にプリントできるデジタルプリントは、アナログプリントのように何度も塗り重ねる手間がありません。
プリント生地では、マリメッコ、ローラアシュレイ、リバティ、モリスなどのテキスタイルブランドが有名です。
生地から選ぶシアーカーテンの生地

薄手で透過性のあるシアーカーテンの生地には、ボイル、オーガンジー、レースなどがあります。 ボイルは平織りの薄い生地で、豊富なカラーバリエーションがあります。 オーガンジーも平織りですが、ハリがあり光沢があるのが特長です。
ラッセル機で編まれたレースは、従来から馴染みのあるレースカーテン生地で、メッシュや多彩な模様があります。 エンブロイダリーレースは、ボイルなどの薄手の生地に刺繍された生地です。
色で選ぶドレープカーテン・シアーカーテン
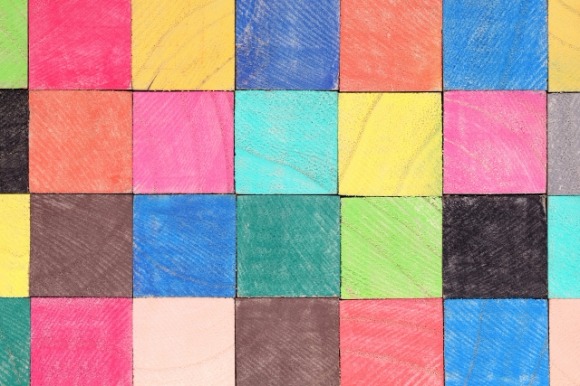
家は、寝室、リビング、子供部屋などそれぞれの部屋にそれぞれの用途があります。カーテンの生地を選ぶ上で、色が与える心理的効果を利用してみることもひとつの方法です。
また部屋のインテリア全体をカラーコーディネートする楽しみ方もあります。
それぞれの方法によるカーテン生地を選ぶポイントを紹介します。
色が与える心理的効果でカーテン選ぶ

色が与える心理的効果や影響は大きく、インテリアをコーディネートする上でも大きな意味を持ちます。
全般的に、暖色系はぬくもりや明るさ、寒色系はクールで落ち着いた雰囲気を感じますが、各色の特性からそれ以外の効果も得られます。

赤
赤色はエネルギッシュな印象を与える一方、部屋全体を赤くすると落ち着かなくなることがあります。赤のカーテンを取り入れる場合は、小さな面積に使ったり、他の色とのバランスを考えたりすると良いでしょう。赤と白のストライプ柄などは、子供部屋だけでなく、リビングやダイニングなどでも活躍します。
青
青は鎮静作用があり、気分を落ち着かせる効果があります。また、寝室や書斎などのリラックスした空間に適しています。濃い青や紺色の生地が落ち着いた印象になります。
緑
カーテンにも緑を取り入れることで、部屋全体がよりリラックスした印象を与えます。例えば、淡いグリーンやオリーブグリーンのカーテンは、落ち着きを与えながらも明るさを保ってくれます。また、自然素材のカーテンなどを選ぶことで、より自然な印象を演出できます。
黄色
黄色は明るく元気な印象を与える色で、創造性やアイデアを刺激する効果があります。しかし、明るすぎる黄色は刺激が強くなりすぎるため、勉強部屋には落ち着いたトーンの黄色を、高齢者の部屋には明るすぎない柔らかい黄色を選ぶとよいでしょう。また、黄色は壁や床材などのインテリア全般でも取り入れると、部屋全体が明るくなり、明るさのある空間になります。
カラーコーディネートを楽しむカーテンの選び方

カーテンのカラーコーディネートにおいては、同系色の組み合わせやコントラストの強い色合わせを避け、トーンを合わせることが大切です。また、カーテン生地によっては、光沢感や質感によって色の印象が変わることもあるので、実際に掛けてみて雰囲気を確認することもおすすめです。
インテリアでは、基調色となる壁や天井の色をベースに、いろいろな色の組み合わせをしながらコーディネートします。同じ色の組み合わせでも、部屋の広さによって狭く感じてしまうこともあるので注意が必要です。失敗しないカラーコーディネートのポイントを覚えて、適したカーテン生地を選びましょう。
同系色でまとめるコーディネート
カーテンと家具を同系色でコーディネートする場合、トーンを変えてメリハリをつけると殺風景になりません。白い壁がベースとなり、茶色の家具であれば、カーテンに同系色のベージュを選ぶと上品なイメージになります。アクセントとなるトーンの濃い色を、少なめに配分にすることがポイントです。
違う色相でカラフルコーディネート
同系色ではなく、黄色、青、赤など違う色相のカラーを複数取り入れたい場合、ビビットトーン、グレイッシュトーン、ペールトーンなど、それぞれのトーンを統一されることで、まとまったイメージになります。カーテンも小物や家具などのカラートーンに合わせて選びましょう。ただし、明度が低い色(暗い色)や彩度が低い色(濃い色)を狭い部屋に使いすぎると圧迫感が出てしまいます。カーテンはある程度の面積を占めるので、柄物にするなど、色の分量を調整する工夫が必要です。
インテリアテイストで決めるカーテンの選び方
カーテンを選ぶ部屋はどのようなイメージですか?インテリアテイストに合わせて、デザインや素材で選ぶ方法です。

北欧インテリアに合うカーテン選びとは
北欧インテリアの特徴は、日照時間が短い冬でも家の中でぬくもりを感じられる明るいインテリアにすることにあります。このテイストに合わせて、北欧デザインのカーテン生地も多く展開されています。植物や動物をモチーフにした柄や、色鮮やかな明るい柄、素朴な柄など、部屋が一気に明るくなるデザインが魅力です。北欧インテリアを取り入れる際には、カーテンのデザインや素材も重要なポイントの一つです。
ヨーロピアンクラシックに合うカーテン選び
ヨーロピアンクラシックのファブリックは、長年にわたって人気が続いています。その高級感ある独特の雰囲気は、重厚な織り柄によって生み出されます。このファブリックを使ったカーテンは、お部屋のグレードをアップさせることができます。ヨーロピアンクラシックのテイストを取り入れたい方は、このファブリックを使用したカーテンがおすすめです。
エレガントな花柄をはじめ、紋をモチーフにしたダマスク柄、唐草模様のアラベスク柄などのジャガード織物が代表的です。ロココ調の格式高いカーテン生地は、和室との相性も良いです。
シックモダンに合うカーテン選び
シックで洗練された大人のインテリアには、シックモダンなカーテンがぴったりです。白やアイボリー、グレー、黒などの無彩色でも、光沢のある生地や幾何学模様などの柄を取り入れることで、地味にならずに印象的な雰囲気を作り出すことができます。特に、一人暮らしの男性に人気があるシックモダンなカーテンは、落ち着いた雰囲気を演出するので、寝室などにもおすすめです。
シンプルナチュラルに合うカーテン選び
ナチュラルテイストの部屋には、素材にこだわったカーテンがぴったりです。特に、天然素材のカーテン生地がおすすめです。代表的な素材としては、綿や麻があります。綿は肌触りが良く、天然素材ならではの吸湿効果や保湿効果がありますが、シワになりやすいことや縮みやすいことが欠点です。一方、麻は通気性が良く丈夫です。
また、麻独特の透け感や自然素材の風合いが魅力的です。天然素材は無地でもその風合いを充分に楽しめますが、柄物を選ぶ場合は、シンプルなチェックやボーダー柄がおすすめです。天然素材のカーテンで、心地よい自然な雰囲気を取り入れましょう。
機能性でカーテンを選ぶ!悩みや用途に合わせたカーテン選び

カーテンには、いろいろな機能性のある生地があります。機能性を重視したい場合の、選び方のポイントをまとめました。
遮光カーテン
部屋の明かりを漏らさない遮光性のあるカーテンは、プライバシーを守ってくれます。また外の明るさも遮るので、朝日のあたる部屋にも有効的です。
遮光機能には1~3等級の段階があります。
1級:99.99%以上(顔の表情が分からないレベル)
2級:99.80%~99.99未満(顔の表情が分かるレベル)
3級:99.40%~99.80未満(事務作業はできないレベル)
遮光性のない生地は99.39%以下です。
遮光等級1級は、学校や病院で使用されている暗幕カーテンなどです。ホームシアターなどを楽しみたい場合は1級が必要ですが、あまり暗すぎると朝になったことも気づかず体内時計が狂うことも。一般住宅なら2~3級で充分でしょう。
遮熱カーテン
遮熱カーテンには、ドレープとレースの両方がありますが、可視光を優先するか、遮熱効果を優先するかで選ぶことがポイントです。夏場に室温上昇の原因となる赤外線を遮る遮熱カーテンは、ドレープの方が効果が高いとされています。暑い夏には窓から入り込む太陽光の赤外線を遮って、室温上昇を防ぎ、快適な室内環境を維持しましょう。
遮熱カーテンには、ドレープとレースの両方がありますが、その遮熱効果についてはドレープの方が高いとされています。しかし、昼間にドレープカーテンを開ける場合は、レースの遮熱カーテンを選ぶことが適しています。一方で、留守にしている時間が長い場合や、西日のあたる部屋など、状況によってはドレープの遮熱カーテンを利用することもおすすめです。適切に使い分けて、快適な室内環境を維持しましょう。
防音カーテン
防音カーテンは、ピアノやヴァイオリンの練習、カラオケ、赤ちゃんの泣き声など、室内の音を外に漏らしたくない場合に最適です。2〜4層で仕立てられ、吸音性に優れているため、室内の音だけでなく、外部からの騒音も防ぐことができます。また、防音効果のあるカーテンには、遮光性や遮熱性を兼ね備えた製品も多くあります。快適な室内環境を維持しながら、防音効果を得るためにも、防音カーテンの利用を検討してみましょう。
消臭カーテン

トイレ臭のアンモニア、腐った魚臭のトリメチルアミン、腐った卵臭の硫化水素、腐った玉ネギ臭のメチルメルカプタンは生活4大悪臭とされています。消臭機能のあるカーテンのメカニズムは、光触媒や酸素触媒を利用して嫌な臭いを分解しています。4大悪臭以外にも、家の中の気になる臭いはいろいろあり、ペット臭やたばこ臭、料理の臭いなどがカーテンに染み込みます。
煙草を吸う方やペットのいる家、キッチンやトイレなどには消臭カーテンがおすすめです。
それぞれの部屋に最適なカーテンを
多方面からカーテンの選び方をご紹介しました。カーテンは、視線や明かりを遮る実用性や室内環境を快適に整える機能性、窓空間を装飾するデザイン性もあります。カーテンを選ぶ際には、その部屋に適した生地を選ぶことです。
カーテンの生地を選ぶことに迷ったら、ぜひ参考にしてください。